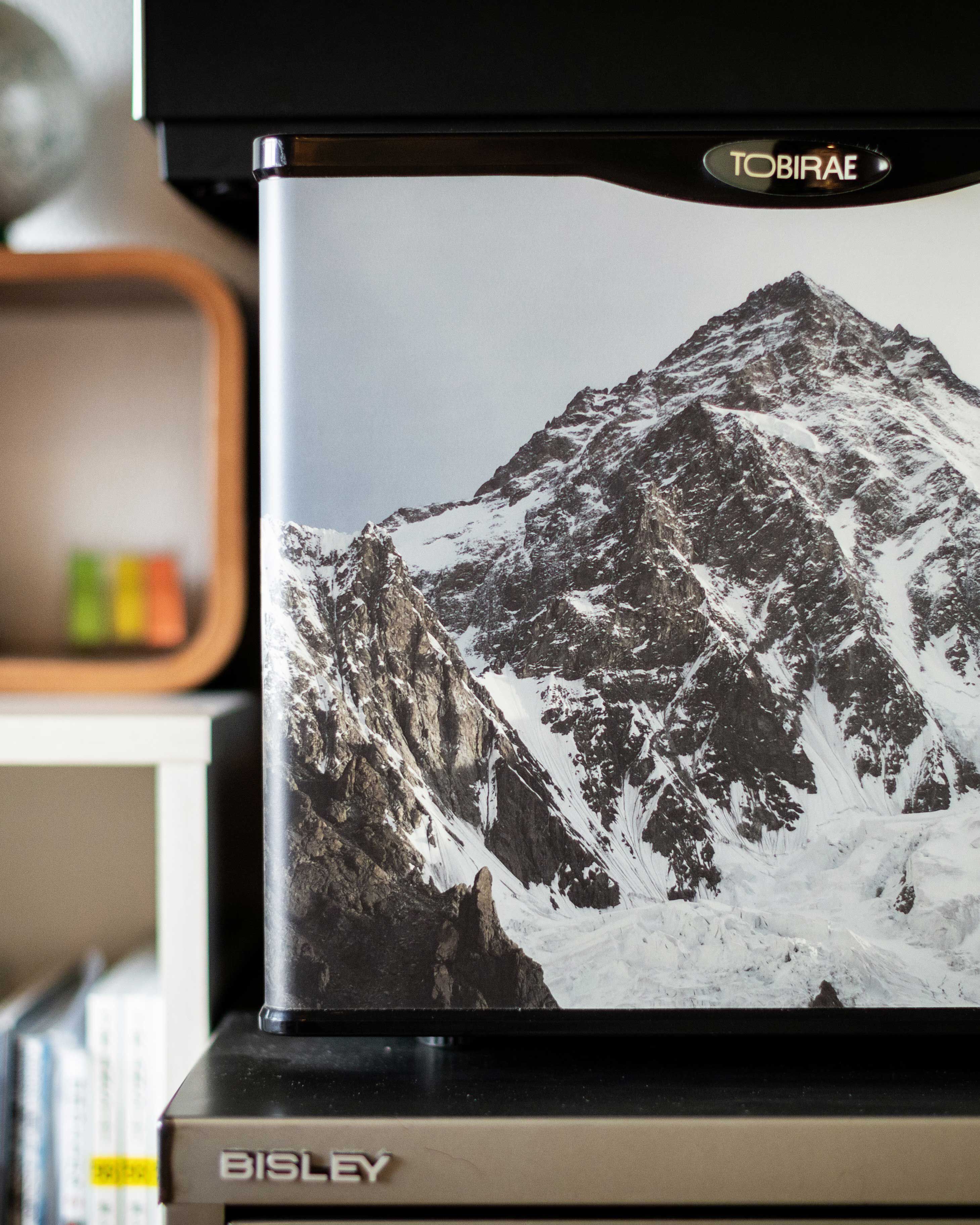"写真家と作家を横断する幅広い表現領域で活動する石川直樹さん。23歳で当時の七大陸最高峰登頂最年少記録を更新し、近年ではヒマラヤの8000メートル峰14座に登り続け、独自の視点で切り取った作品を発表しつづけています。そんな石川さんに、これまでの旅やヴィブラムとの出会いについて語っていただきました。(取材日:2024年6月)
−− 石川さんは写真家、作家、そして登山や冒険など活動が多岐にわたりますが、ご自身についてどのように捉えていますか?
石川 肩書きというものにあまり意味を感じませんね。自分が旅を通じて見てきたものを写真や文章で記録し、様々な形でアウトプットしていく、ということを長年続けてきました。旅することと写真を撮ることは分かちがたく結びついていて、どこかで区切られるものではありません。
−− これまでヒマラヤの山々をはじめ、世界中のさまざまな場所を訪れてきました。旅への情熱はいつごろ芽生えたのでしょうか?
石川 高校2年生のときにインドとネパールを一人旅したのがきっかけです。このときは、海の向こうに日本とは異なる文化があり、世界は極めて多様である、という当たり前の事実を、17歳という年齢で身をもって実感しました。 ご飯を手で食べる、トイレでは紙を使わず手で拭く、人々が行き交う道路をゾウが歩いている、ガンジス川の上流から遺体が流れてくるなどなど……インターネットやガイドブックで知っているつもりになっているのと、実際にその場に身を置いて“出会う”のとでは、大きな違いがあります。17歳のぼくには衝撃的で、そのような体験がその後の旅への契機になりました。さまざまな未知のものに出会い、五感で知覚し、理解していく……それを体現しているのが旅だと思っています。
−− 20歳でアラスカのデナリに登頂し、22歳のときに北極から南極までの地球縦断プロジェクトに参加されましたね。
石川 デナリは標高が6190メートルで北米大陸最高峰の山ですが、いわば垂直方向への旅である高所登山の魅力を教えてくれました。 地球縦断プロジェクト『POLE TO POLE』では、自転車、カヌー、スキーなど人力の移動手段を使い、国際チームで1年かけて北極から南極へ縦断しました。地球を半周するわけですが、北極から北米、中米、南米、そして南極と、環境が徐々に変わっていくさまを身体で経験できたのがよかったですね。 また、世界7カ国から集まった8人の同世代のメンバーによる旅だったので、言葉も文化も異なる仲間とのコミュニケーションや共同生活について、難しさや楽しさを知りました。1年間の旅でしたが、学校などに通うより何倍も多くのことを学ぶことができたと思っています。
−− ヴィブラムとの出会いもその頃ですか?
石川 「ダナーライト」という、ヴィブラムのソールを使った靴があるのですが、それを高校生のころに履きはじめたのがきっかけです。街でも自然の中でも履き込んでいたので、結局ソールを3回ほど交換して使っていました。使いすぎてブーツ本体も傷んでしまい2足目を購入しました。 アフリカ大陸の最高峰であるキリマンジャロなど、標高6000メートルくらいまでならダナーライトで登っていました。とにかくアウトソールがヴィブラムというだけで安心感がありましたね。それ以来、ヴィブラムとは30年の長い付き合いで、トレッキングシューズでも登山靴でもヴィブラムのアウトソールの靴を無数に履いてきました。
−− 2001年に23歳でエベレスト登頂に成功し、七大陸最高峰登頂最年少記録を更新(当時)されました。かつて、英国の登山家でエベレスト登山中に遭難したジョージ・マロリーは「なぜエベレストに登るのか?」という問いに対し「そこにエベレストがあるから」と答えたという逸話があります。石川さんはなぜ世界の頂点を目指したのでしょうか?
石川 その話は、ただ山があるから、という意味ではなく、未踏峰としてのエベレストがそこにあったから、という意味ですね。旅を突き詰めていくと、どうしてもガイドブックなどに出ていない場所、情報が少ない場所へ行ってみたくなります。エベレストは今では多くの人が登っていますが、ぼくはそれでも最高峰の山というものを体感してみたかったですね。
−− そのときも足元はヴィブラムでしたか?
石川 はい。2001年のときはミレーの靴で、2011年にもう一度登った時はイタリアの「SCARPA(スカルパ)」のトレッキングシューズと登山靴を履いていて、いずれもアウトソールはヴィブラムでした。エベレストのベースキャンプは標高5300メートル辺りなのですが、そこまではトレッキングシューズで。ベースキャンプより先は氷河なので、アイゼンを装着します。
−− 標高8000メートルの世界では空気中の酸素濃度が地上の約1/3まで低下し、人間が生存するのが難しいことから「デスゾーン」と言われますが、実際に体験されていかがでしたか?
石川 ただ、ぼくは酸素ボンベを使っていますからね。それでも、大変ではありますが。本当に生き延びようという強い意志を持たないと、命を失いかねない場所です。6000メートル峰とは、全然異なる感覚がありました。登頂時はもちろん嬉しいのですが、下山の際に遭難する可能性も高いので、早くベースキャンプまで戻りたい、という気持ちが強いです。
−− そのような苛酷な状況において、どのような思いでシャッターを切るのでしょうか?
石川 自分の身体が反応した瞬間にシャッターを切ります。理想は見たものすべてを写真に記録していくことですが、さすがにそれは難しい。そこで、自分が目にして、何か「オッ」と感じたものを撮っていくイメージです。それは、ヒマラヤの山でも東京でも変わりません。 自分が見て身体が反応したものを撮影し、それを写真展や写真集のような形で経験を分かち合ってきました。同時代の人に見てもらいたい気持ちはもちろんありますが、写真は50年後、100年後まで残るので、未来の人々に「こういう風景があったんだよ」ということを伝えたいという気持ちも込めて写真集を編んでいます。展示は見られる人が限られますが、写真集は長く残りますから。
−− 自分の作品を通して、どんなことを伝えたいですか?
石川 何かを伝えたいのではなく、自分が出会ってきたものをそのまま提示したいと考えています。ぼくの写真から地球環境のことを考える人がいてもいいし、写っている人々の暮らしや文化に興味を持つ人がいてもいいし、あるいは美しい風景に心を動かされる人がいてもいいし、あるいは何も感じなくたっていい……見る人に自由に見てもらいたいです。
−− そもそも写真に目覚めたきっかけは?
石川 高校時代にインドとネパールを訪れたときからずっと、旅にカメラを携えていました。目の前のものを記録しておきたい、という気持ちが強かったのだと思います。その後、森山大道さんをはじめとする個性的で優れた写真家たちとの出会いが大きかったですね。
−− 2001年のエベレスト登頂後は、ポリネシアの島々を巡ったり、世界中の先史時代の洞窟壁画を撮影したり、さまざまな写真集を発表してきましたが、2011年に再びエベレストを目指されましたね。
石川 2001年に登頂したときはチベット側のルートからでしたが、ネパール側から登ってくる登山隊もいて、いつか自分も行ってみたいなあ、と思ったんです。そこで、ちょうど10年後の2011年に、今度はネパール側からのルートで登ってみました。そのときにヒマラヤ登山の面白さに改めて気づいて、その後、毎年のように他の8000メートル峰に挑戦するようになりました。
石川直樹 写真家
−− 石川さんは写真家、作家、そして登山や冒険など活動が多岐にわたりますが、ご自身についてどのように捉えていますか?
石川 肩書きというものにあまり意味を感じませんね。自分が旅を通じて見てきたものを写真や文章で記録し、様々な形でアウトプットしていく、ということを長年続けてきました。旅することと写真を撮ることは分かちがたく結びついていて、どこかで区切られるものではありません。
−− これまでヒマラヤの山々をはじめ、世界中のさまざまな場所を訪れてきました。旅への情熱はいつごろ芽生えたのでしょうか?
石川 高校2年生のときにインドとネパールを一人旅したのがきっかけです。このときは、海の向こうに日本とは異なる文化があり、世界は極めて多様である、という当たり前の事実を、17歳という年齢で身をもって実感しました。 ご飯を手で食べる、トイレでは紙を使わず手で拭く、人々が行き交う道路をゾウが歩いている、ガンジス川の上流から遺体が流れてくるなどなど……インターネットやガイドブックで知っているつもりになっているのと、実際にその場に身を置いて“出会う”のとでは、大きな違いがあります。17歳のぼくには衝撃的で、そのような体験がその後の旅への契機になりました。さまざまな未知のものに出会い、五感で知覚し、理解していく……それを体現しているのが旅だと思っています。
−− 20歳でアラスカのデナリに登頂し、22歳のときに北極から南極までの地球縦断プロジェクトに参加されましたね。
石川 デナリは標高が6190メートルで北米大陸最高峰の山ですが、いわば垂直方向への旅である高所登山の魅力を教えてくれました。 地球縦断プロジェクト『POLE TO POLE』では、自転車、カヌー、スキーなど人力の移動手段を使い、国際チームで1年かけて北極から南極へ縦断しました。地球を半周するわけですが、北極から北米、中米、南米、そして南極と、環境が徐々に変わっていくさまを身体で経験できたのがよかったですね。 また、世界7カ国から集まった8人の同世代のメンバーによる旅だったので、言葉も文化も異なる仲間とのコミュニケーションや共同生活について、難しさや楽しさを知りました。1年間の旅でしたが、学校などに通うより何倍も多くのことを学ぶことができたと思っています。
−− ヴィブラムとの出会いもその頃ですか?
石川 「ダナーライト」という、ヴィブラムのソールを使った靴があるのですが、それを高校生のころに履きはじめたのがきっかけです。街でも自然の中でも履き込んでいたので、結局ソールを3回ほど交換して使っていました。使いすぎてブーツ本体も傷んでしまい2足目を購入しました。 アフリカ大陸の最高峰であるキリマンジャロなど、標高6000メートルくらいまでならダナーライトで登っていました。とにかくアウトソールがヴィブラムというだけで安心感がありましたね。それ以来、ヴィブラムとは30年の長い付き合いで、トレッキングシューズでも登山靴でもヴィブラムのアウトソールの靴を無数に履いてきました。
−− 2001年に23歳でエベレスト登頂に成功し、七大陸最高峰登頂最年少記録を更新(当時)されました。かつて、英国の登山家でエベレスト登山中に遭難したジョージ・マロリーは「なぜエベレストに登るのか?」という問いに対し「そこにエベレストがあるから」と答えたという逸話があります。石川さんはなぜ世界の頂点を目指したのでしょうか?
石川 その話は、ただ山があるから、という意味ではなく、未踏峰としてのエベレストがそこにあったから、という意味ですね。旅を突き詰めていくと、どうしてもガイドブックなどに出ていない場所、情報が少ない場所へ行ってみたくなります。エベレストは今では多くの人が登っていますが、ぼくはそれでも最高峰の山というものを体感してみたかったですね。
−− そのときも足元はヴィブラムでしたか?
石川 はい。2001年のときはミレーの靴で、2011年にもう一度登った時はイタリアの「SCARPA(スカルパ)」のトレッキングシューズと登山靴を履いていて、いずれもアウトソールはヴィブラムでした。エベレストのベースキャンプは標高5300メートル辺りなのですが、そこまではトレッキングシューズで。ベースキャンプより先は氷河なので、アイゼンを装着します。
−− 標高8000メートルの世界では空気中の酸素濃度が地上の約1/3まで低下し、人間が生存するのが難しいことから「デスゾーン」と言われますが、実際に体験されていかがでしたか?
石川 ただ、ぼくは酸素ボンベを使っていますからね。それでも、大変ではありますが。本当に生き延びようという強い意志を持たないと、命を失いかねない場所です。6000メートル峰とは、全然異なる感覚がありました。登頂時はもちろん嬉しいのですが、下山の際に遭難する可能性も高いので、早くベースキャンプまで戻りたい、という気持ちが強いです。
−− そのような苛酷な状況において、どのような思いでシャッターを切るのでしょうか?
石川 自分の身体が反応した瞬間にシャッターを切ります。理想は見たものすべてを写真に記録していくことですが、さすがにそれは難しい。そこで、自分が目にして、何か「オッ」と感じたものを撮っていくイメージです。それは、ヒマラヤの山でも東京でも変わりません。 自分が見て身体が反応したものを撮影し、それを写真展や写真集のような形で経験を分かち合ってきました。同時代の人に見てもらいたい気持ちはもちろんありますが、写真は50年後、100年後まで残るので、未来の人々に「こういう風景があったんだよ」ということを伝えたいという気持ちも込めて写真集を編んでいます。展示は見られる人が限られますが、写真集は長く残りますから。
−− 自分の作品を通して、どんなことを伝えたいですか?
石川 何かを伝えたいのではなく、自分が出会ってきたものをそのまま提示したいと考えています。ぼくの写真から地球環境のことを考える人がいてもいいし、写っている人々の暮らしや文化に興味を持つ人がいてもいいし、あるいは美しい風景に心を動かされる人がいてもいいし、あるいは何も感じなくたっていい……見る人に自由に見てもらいたいです。
−− そもそも写真に目覚めたきっかけは?
石川 高校時代にインドとネパールを訪れたときからずっと、旅にカメラを携えていました。目の前のものを記録しておきたい、という気持ちが強かったのだと思います。その後、森山大道さんをはじめとする個性的で優れた写真家たちとの出会いが大きかったですね。
−− 2001年のエベレスト登頂後は、ポリネシアの島々を巡ったり、世界中の先史時代の洞窟壁画を撮影したり、さまざまな写真集を発表してきましたが、2011年に再びエベレストを目指されましたね。
石川 2001年に登頂したときはチベット側のルートからでしたが、ネパール側から登ってくる登山隊もいて、いつか自分も行ってみたいなあ、と思ったんです。そこで、ちょうど10年後の2011年に、今度はネパール側からのルートで登ってみました。そのときにヒマラヤ登山の面白さに改めて気づいて、その後、毎年のように他の8000メートル峰に挑戦するようになりました。
石川直樹 写真家
現在、8000メートル峰14座登頂の完遂を目前に控える石川直樹さん。ヒマラヤ登山の相棒にヴィブラムを選ぶ理由とは?
最高峰のエベレストをはじめ世界中の山々や辺境の地を旅し、そこで撮影した作品を発表しつづけている写真家の石川直樹さん。ところで、地球上には標高8000メートル以上の山が14座存在し、そのすべてがヒマラヤ山脈に位置しています。14座すべてに登頂した登山家は敬意を込めて「14サミッター」と称されますが、世界でも40数名、日本にはたった1名しかいません。石川さんはこれまで13座の登頂に成功し、14サミッターに王手をかけています。後編では、そんな石川さんにヒマラヤ登山での体験やヴィブラムを選ぶ理由について語っていただきました。(取材日:2024年6月)
−− 2011年に2度目のエベレスト登頂を果たして以来、毎年のようにヒマラヤを訪れていますね。
石川
ヒマラヤ登山の面白さを再認識して、12年にはマナスル、13年にはローツェ、14年にはマカルーに登頂しました。遠征では約2カ月ほどで、標高5000メートル以上の高所で過ごす日々も多くなります。その間は食生活や呼吸法も普段の生活とはちょっと変わってきます。一言でいえば「生きる」ことに対して意識的になる。そんな日々が続くと、自分の身体にこびりついていた澱のようなものが消えて、リセットされるような感覚になるんです。そんな感覚が好きなのも、ヒマラヤに通う理由かもしれません。
−− いつごろから14座制覇を意識したのですか?
石川
決して簡単なことではないし、志半ばで遭難して命を落とす登山家も多いので、当時は14座すべてに登ろうとは考えていませんでした。毎年のようにヒマラヤを訪れているうちに信頼できるシェルパの友だちが増え、彼らから「あの山に登ろう」「この山に登ろう」と声をかけてもらうようになったんです。自分でもヒマラヤ登山が楽しくて彼らと一緒に登っているうちに13座に登頂していたという感じです。
−− コロナ禍によるブランクを経て、22年には7位のダウラギリ(8167メートル)、3位のカンチェンジュンガ(8586メートル)、2位のK2(8611メートル)、そして23年には10位のアンナプルナ(8091メートル)、9位のナンガ・パルパット(8126メートル)、11位のガッシャープルム1峰(8068メートル)、6位のチョ・オユー(8201メートル)と、たった2年で驚異的なペースでヒマラヤの8000メートル峰に登頂しましたね。
石川
やはりコロナ禍で海外に行けない時期が長かったので……。ぼくの場合、体が高所に順応しているうちに立て続けに登ったほうが、期間を空けて一から順応し直して登るより楽なんです。ぼくの場合、というかみんなそうなんじゃないかな。だから、一年に何座登頂したからすごい、という感覚はまったくないですね。
−− これまで登頂した13座で特に印象深い山は?
石川
いずれもその山ならではの特徴や魅力があって、それぞれに思い出があるので選ぶのは難しいです。K2は雪崩に巻き込まれたりして2度失敗したし、チョ・オユーは比較的登りやすい山だといわれているけれど、ホワイトアウトになって何時間も頂上付近を彷徨ったし、振り返るとすべての山に特別な思い出があります。
−− 14座目となるシシャパンマについてはいかがですか?
石川
標高は8027メートルで14座中もっとも低いのですが、決して簡単な山ではありません。中央峰と主峰という2つのピークがあり、真の頂上である主峰に登ろうとすると、最後のトラバースがすごく大変で。何年も前は、みんな中央峰に登って登頂とみなしてきた時代があったのですが、やっぱり本当の頂上に立たないと気持ち悪いというか。
2023年に挑戦したときは、頂上まであと一歩のところで雪崩に遭遇して撤退しました。この春にも登るつもりだったのですが、中国政府からチベットへの入境許可がおりず、ネパールに1カ月間足止めされて、そのまま帰国しました。この9月から10月にかけて再チャレンジする予定です。今回こそは登頂できたらなあ、と。
−− これまで雪崩やホワイトアウトなど幾多の難局に直面してきたわけですが、共に乗り越えてきたシェルパやスタッフについてお聞かせください。
石川
ぼくは日本で知り合いはたくさんいますが、本当に友だちだ、といえる人は決して多くありません。でも、シェルパには友だちといえる人が何人もいます。やはり弱い部分もさらけ出しながら1、2カ月間行動を共にすると、奥底で通じ合えるような感覚が芽生えるんですよ。人間はピンチなときに本性が出ますが、それでもなお人のことを気遣えるシェルパの友人たちは本当に信頼できますね。
−− 道具やギアについても信頼感ですよね。
石川
道具選びはとても重要で、生死に関わることなので機能性がまず第一です。もちろん自分好みの色やデザインであることも大切ですが、「形態は機能に従う」じゃないけれど、機能性をとことん追求していくと、どんなものでも美しくなる。だから、機能性を最重視しています。
−− ヴィブラムを30年使いつづけているのも、信頼しているからですね?
石川
そうですね。アウトソールがヴィブラムというだけでまあ大丈夫だろう、みたいな感じで、例のイエローのマークは僕にとって安心の証しです。実際、これまで登頂した8000メートル峰13座はすべてヴィブラムが付いた靴で登ってきました。後半の山はすべてスカルパの靴で登頂しましたね。
−− 何かヴィブラムの性能を実感したエピソードはありますか?
石川
たとえばK2ではバルトロという氷河を1週間以上歩きつづけなければならないのですが、尖った岩から氷河の氷にいたるまでとにかく足元の状態が極めて多様で、悪いんですよね。そのときのトレッキングシューズもヴィブラムが付いていたのですが、グリップ感といい、ソール自体の硬さといい、信頼感がありました。ソールが柔らかすぎると、ケガをしたりする危険性も高いので。
−− 先ほどエベレストの話で、5300メートルのベースキャンプから先は氷河のためヴィブラムのアウトソールにアイゼンを装着して登るとのことでしたね。
石川
標高5000メートル以上では氷河になるのでアイゼンを装着します。ヴィブラムのアウトソールは頑丈なので、もちろんソールがはがれたり、破損したりすることはないです。アイゼンは、コバといってソールのつま先やかかと部分にある溝に引っかけて装着するのですが、コバが破損でもしてアイゼンが外れたら滑落してしまいますから、強度の高いソールを選ぶことは命を守ることでもあるのです。
−− 目下のテーマであるシシャパンマ登頂もヴィブラムの靴で?
石川
もちろんです。8000メートル峰に挑戦するうえで、アウトソールはヴィブラム以外の選択肢はありません。
−− ところで、ヴィブラムはイタリア発祥のブランドですが、イタリアの山に登ったことはありますか?
石川
イタリア北部のオロビエアルプスの山々にはいくつも登りました。イタリアの山は日暮れから夜明け前はどこにでもテントが張れるんです。日本では夏だとテント場が決められていますが、そもそもテントは命を守るエマージェンシー・ギアという側面もあるわけだし、イタリアは登山者を大人扱いしている印象を受けました。
オロビエアルプスは標高2000〜3000メートルの山々が連なっていて景色が美しく、山小屋のネットワークも発達しているし、地元の山岳会がしっかり機能しています。イタリアならではの成熟した山岳文化を感じました。
−− やはりイタリアにはヴィブラムのようなブランドを育む山岳文化が根付いているんですね。
石川
イタリアといえば、この8月にはシチリア島のエトナ火山に登って撮影する予定です。もちろん、そのときにもヴィブラムのトレッキングシューズを履きます。
−− シンシャパンマ挑戦と並行して他のプロジェクトも動いているわけですね。8000メートル峰14座完登後の計画はありますか?
石川
二年後くらいに美術館で大規模な個展が予定されていて、それに向けて写真を撮り進めています。知床半島や能登半島など日本の半島を巡って、海から見た日本を見つめなおしたり
−− 目下の目標であるこの秋のシシャパンマ登頂を心からお祈りしていますが、2年後の写真展も楽しみにしています。本日はありがとうございました。
8000メートル峰14座完登という偉業を目前に控え、そしてその先の新たなる挑戦に向けて、石川直樹さんの歩みは続く。その足取りを支えるのは、常にヴィブラムのソールなのだ。そして、その靴底が刻む足跡は、これからも私たちに新たな世界を見せてくれることだろう。
石川直樹
写真家
1977年東京都生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。2008年『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞。2011年『CORONA』(青土社)により土門拳賞。2020年『EVEREST』(CCCメディアハウス)、『まれびと』(小学館)により日本写真協会賞作家賞。2023年 東川賞特別作家賞。2024年紺綬褒章を受賞した。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)、『地上に星座をつくる』(新潮社)ほか多数。
最高峰のエベレストをはじめ世界中の山々や辺境の地を旅し、そこで撮影した作品を発表しつづけている写真家の石川直樹さん。ところで、地球上には標高8000メートル以上の山が14座存在し、そのすべてがヒマラヤ山脈に位置しています。14座すべてに登頂した登山家は敬意を込めて「14サミッター」と称されますが、世界でも40数名、日本にはたった1名しかいません。石川さんはこれまで13座の登頂に成功し、14サミッターに王手をかけています。後編では、そんな石川さんにヒマラヤ登山での体験やヴィブラムを選ぶ理由について語っていただきました。(取材日:2024年6月)
−− 2011年に2度目のエベレスト登頂を果たして以来、毎年のようにヒマラヤを訪れていますね。
石川
ヒマラヤ登山の面白さを再認識して、12年にはマナスル、13年にはローツェ、14年にはマカルーに登頂しました。遠征では約2カ月ほどで、標高5000メートル以上の高所で過ごす日々も多くなります。その間は食生活や呼吸法も普段の生活とはちょっと変わってきます。一言でいえば「生きる」ことに対して意識的になる。そんな日々が続くと、自分の身体にこびりついていた澱のようなものが消えて、リセットされるような感覚になるんです。そんな感覚が好きなのも、ヒマラヤに通う理由かもしれません。
−− いつごろから14座制覇を意識したのですか?
石川
決して簡単なことではないし、志半ばで遭難して命を落とす登山家も多いので、当時は14座すべてに登ろうとは考えていませんでした。毎年のようにヒマラヤを訪れているうちに信頼できるシェルパの友だちが増え、彼らから「あの山に登ろう」「この山に登ろう」と声をかけてもらうようになったんです。自分でもヒマラヤ登山が楽しくて彼らと一緒に登っているうちに13座に登頂していたという感じです。
−− コロナ禍によるブランクを経て、22年には7位のダウラギリ(8167メートル)、3位のカンチェンジュンガ(8586メートル)、2位のK2(8611メートル)、そして23年には10位のアンナプルナ(8091メートル)、9位のナンガ・パルパット(8126メートル)、11位のガッシャープルム1峰(8068メートル)、6位のチョ・オユー(8201メートル)と、たった2年で驚異的なペースでヒマラヤの8000メートル峰に登頂しましたね。
石川
やはりコロナ禍で海外に行けない時期が長かったので……。ぼくの場合、体が高所に順応しているうちに立て続けに登ったほうが、期間を空けて一から順応し直して登るより楽なんです。ぼくの場合、というかみんなそうなんじゃないかな。だから、一年に何座登頂したからすごい、という感覚はまったくないですね。
−− これまで登頂した13座で特に印象深い山は?
石川
いずれもその山ならではの特徴や魅力があって、それぞれに思い出があるので選ぶのは難しいです。K2は雪崩に巻き込まれたりして2度失敗したし、チョ・オユーは比較的登りやすい山だといわれているけれど、ホワイトアウトになって何時間も頂上付近を彷徨ったし、振り返るとすべての山に特別な思い出があります。
−− 14座目となるシシャパンマについてはいかがですか?
石川
標高は8027メートルで14座中もっとも低いのですが、決して簡単な山ではありません。中央峰と主峰という2つのピークがあり、真の頂上である主峰に登ろうとすると、最後のトラバースがすごく大変で。何年も前は、みんな中央峰に登って登頂とみなしてきた時代があったのですが、やっぱり本当の頂上に立たないと気持ち悪いというか。
2023年に挑戦したときは、頂上まであと一歩のところで雪崩に遭遇して撤退しました。この春にも登るつもりだったのですが、中国政府からチベットへの入境許可がおりず、ネパールに1カ月間足止めされて、そのまま帰国しました。この9月から10月にかけて再チャレンジする予定です。今回こそは登頂できたらなあ、と。
−− これまで雪崩やホワイトアウトなど幾多の難局に直面してきたわけですが、共に乗り越えてきたシェルパやスタッフについてお聞かせください。
石川
ぼくは日本で知り合いはたくさんいますが、本当に友だちだ、といえる人は決して多くありません。でも、シェルパには友だちといえる人が何人もいます。やはり弱い部分もさらけ出しながら1、2カ月間行動を共にすると、奥底で通じ合えるような感覚が芽生えるんですよ。人間はピンチなときに本性が出ますが、それでもなお人のことを気遣えるシェルパの友人たちは本当に信頼できますね。
−− 道具やギアについても信頼感ですよね。
石川
道具選びはとても重要で、生死に関わることなので機能性がまず第一です。もちろん自分好みの色やデザインであることも大切ですが、「形態は機能に従う」じゃないけれど、機能性をとことん追求していくと、どんなものでも美しくなる。だから、機能性を最重視しています。
−− ヴィブラムを30年使いつづけているのも、信頼しているからですね?
石川
そうですね。アウトソールがヴィブラムというだけでまあ大丈夫だろう、みたいな感じで、例のイエローのマークは僕にとって安心の証しです。実際、これまで登頂した8000メートル峰13座はすべてヴィブラムが付いた靴で登ってきました。後半の山はすべてスカルパの靴で登頂しましたね。
−− 何かヴィブラムの性能を実感したエピソードはありますか?
石川
たとえばK2ではバルトロという氷河を1週間以上歩きつづけなければならないのですが、尖った岩から氷河の氷にいたるまでとにかく足元の状態が極めて多様で、悪いんですよね。そのときのトレッキングシューズもヴィブラムが付いていたのですが、グリップ感といい、ソール自体の硬さといい、信頼感がありました。ソールが柔らかすぎると、ケガをしたりする危険性も高いので。
−− 先ほどエベレストの話で、5300メートルのベースキャンプから先は氷河のためヴィブラムのアウトソールにアイゼンを装着して登るとのことでしたね。
石川
標高5000メートル以上では氷河になるのでアイゼンを装着します。ヴィブラムのアウトソールは頑丈なので、もちろんソールがはがれたり、破損したりすることはないです。アイゼンは、コバといってソールのつま先やかかと部分にある溝に引っかけて装着するのですが、コバが破損でもしてアイゼンが外れたら滑落してしまいますから、強度の高いソールを選ぶことは命を守ることでもあるのです。
−− 目下のテーマであるシシャパンマ登頂もヴィブラムの靴で?
石川
もちろんです。8000メートル峰に挑戦するうえで、アウトソールはヴィブラム以外の選択肢はありません。
−− ところで、ヴィブラムはイタリア発祥のブランドですが、イタリアの山に登ったことはありますか?
石川
イタリア北部のオロビエアルプスの山々にはいくつも登りました。イタリアの山は日暮れから夜明け前はどこにでもテントが張れるんです。日本では夏だとテント場が決められていますが、そもそもテントは命を守るエマージェンシー・ギアという側面もあるわけだし、イタリアは登山者を大人扱いしている印象を受けました。
オロビエアルプスは標高2000〜3000メートルの山々が連なっていて景色が美しく、山小屋のネットワークも発達しているし、地元の山岳会がしっかり機能しています。イタリアならではの成熟した山岳文化を感じました。
−− やはりイタリアにはヴィブラムのようなブランドを育む山岳文化が根付いているんですね。
石川
イタリアといえば、この8月にはシチリア島のエトナ火山に登って撮影する予定です。もちろん、そのときにもヴィブラムのトレッキングシューズを履きます。
−− シンシャパンマ挑戦と並行して他のプロジェクトも動いているわけですね。8000メートル峰14座完登後の計画はありますか?
石川
二年後くらいに美術館で大規模な個展が予定されていて、それに向けて写真を撮り進めています。知床半島や能登半島など日本の半島を巡って、海から見た日本を見つめなおしたり
−− 目下の目標であるこの秋のシシャパンマ登頂を心からお祈りしていますが、2年後の写真展も楽しみにしています。本日はありがとうございました。
8000メートル峰14座完登という偉業を目前に控え、そしてその先の新たなる挑戦に向けて、石川直樹さんの歩みは続く。その足取りを支えるのは、常にヴィブラムのソールなのだ。そして、その靴底が刻む足跡は、これからも私たちに新たな世界を見せてくれることだろう。
石川直樹
写真家
1977年東京都生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。2008年『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞。2011年『CORONA』(青土社)により土門拳賞。2020年『EVEREST』(CCCメディアハウス)、『まれびと』(小学館)により日本写真協会賞作家賞。2023年 東川賞特別作家賞。2024年紺綬褒章を受賞した。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)、『地上に星座をつくる』(新潮社)ほか多数。